減薬・断薬へのスタートライン~「服薬根拠はわかりません」~
減薬・断薬へのスタートライン ~「服薬根拠はわかりません」~

施設長 李在一
「児童青年精神医学」という本が明石書店から出されている。これはマイケル・ラターとエリック・テイラーが編集したものを「日本小児精神医学研究会」が訳したものだ。高さ30cm、厚さ7cm、重さ3.5kの代物。この本は見た目には権威的ながらも読みやすくわかりやすい解説で、知りたい事象の周辺事情にも言及されている。利用者の状況を理解するために幾度もこの本のページをめくったものであった。
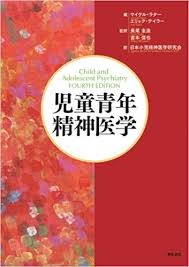
さて、「精神医学」を統計学的見地から否定できる論理(2016年小倉謙氏)に出会うまで、それでも皮肉なことに私が利用者に対する服薬に疑問の確信をもったのもこの本の影響であった。第59章P-1167、「薬物療法とその他の身体的治療」という章において次の記述がある。該当部分を以下にそのまま引用する。
子どもに投薬を試みる医師は、次の7点を検討すべきである。
1. その子どもは薬物療法に対して反応することがわかっている標的症状を
持っているのか。
2. その症状はどれだけ重度であるのか、またその子の治療目標は何なのか。
3. その子どもの状態のうち、どの症状が薬物によって改善されそうなのか、
またはどの症状が改善されそうにないのか。
4. 治療への反応の見込みはどうか(これまでの治療の実績とその症例につ
いての判断から)。
5. 薬物療法の利益と危険性(副作用)のバランスはどうか。短期使用と長
期使用の双方を含めて。
6. 治療への反応と治療成績はどのように評価されているのか。
7. 薬物への危険性(副作用)のチェック(血液検査など)は必要か。
ほぼすべてのケースで、薬物療法は精神障害を有する子どもにとって治療手段の1つにすぎず、その他心理学的、社会的、治療教育的介入がなされるべきであろう。たとえ薬物療法がかなり有用な治療法であっても、その他なされていない多くの治療法があり、薬物療法はほぼ常に、多面的な治療手段の1つとして位置づけられているにすぎない。例えば、トゥレット症候群のチック症状は、ドーパミン拮抗薬に対して高率によく反応するが、これも治療の重要な一手段であろう。この薬はかなりの副作用を示すことが知られている・・・(引用終了)

さて、施設利用者における薬物療法について上記の7点が検討されているという実態は私が知る限りにおいて存在していない。またかつて検討されたという痕跡さえ見出すことはできなかった。施設では服薬は医師の専決事項の範囲であり、さながらその代理者として施設に所属する看護師の占有と化していた。支援員たちは何も考える必要がなく指示された服薬をルーティン業務として機械的に繰り返す状態であった。仮に精神抗薬等の危険な副作用に対する懸念を表明したところで、医学用語を駆使した看護師たちがかもしだす聖域意識によって施設内で薬物療法が真摯に検討されることは皆無であった。そういった医師の権威に看護師や施設管理者らが従属してしまえば副作用の危険性が施設で建設的に議論されることは、少なくとも私の体験上からすればありえないといってまちがいない。かつて私は何度も薬物療法における危険性について問題提起を試みたが、端的にいえば例外なく無視という形の結末になった。ありていにいえば素人の私が、素人なりに職員らに服薬における医師への疑問を指摘しても、どうなるものではないという構造的な帰結であった。
そもそも薬の処方は例外なく医師が実施するという前提が自明のものとしてあるが、自己決定が可能な健常者であれば良し悪しはともかくそうした医師による処方を本人自身が気分次第で無視することもできる。たとえば高齢者が医師から処方された薬を大量にあられの缶などにため込んでいる事象などもそういう「無視」に該当するであろう。高齢者らは医師が処方する薬が危険であることを本能的あるいは体験上から知っている場合が少なくない。
だが自己決定が希薄とされる知的障害者の場合は、医師の処方決定が他者(施設職員)によって強制的かつ半永久的に補強されて実施されるという状態をたどることになる。
補強というのは、もし仮に服薬における自己決定が可能であれば、よほどの必要性を自覚しない限り、毎日決まった時間に服薬するというのはかなり緻密な性格でない限り、いつの間にか服薬を忘れてしまうものではないか。そうして服薬を忘れても自己の体に何も影響がなければ、服薬に伴うめんどうくささから結果的にいつの間にか断薬になる場合も少なくない。
ところが施設では医師が処方した通り、職員が利用者に服薬させる。もし仮に服薬を忘れたとなると、その者は「事故報告書」を施設に提出し、再発防止に全職員が努めなければならない。つまり医師の処方通りの服薬が徹底されるという意味においての「補強」である。

遠慮なく指摘するならば、こうした服薬状況には次に述べる問題あるいは疑問がある。服薬の処方は医師に100%ゆだねられているが、それを受け入れるか否かについては患者に絶対的権限がある。現実にはまず拒否できる患者の自由裁量があって服薬の処方が医師にゆだねられている構図がある。つまり医師がどのような処方をしようが相手が「自己決定できる健常者」であるなら、医師の処方を実現するためには少なくとも「自己決定できる健常者」というハードルを越えなくてはならない。ところが「自己決定が希薄とされる知的障害者」にはそのハードルが存在していない。ハードルが存在していないから、医師による処方がそのまま完全に反映される形で実現されることになる。
医師の処方が100%実現されるわけだから、客観的かつ一般的には何の問題もないかのように映ることであろう。しかし医師が医師免許を取得するために学ぶ学科の中に知的障害者の特性について教えている学科は存在していない。例外といえるのは歯科医師の資格取得の中にあるだけだ。つまりよほどの例外を除いて医師は知的障害の専門性を有していない。医師にあるのはどこまでいっても対象が「健常者」であるということ、つまり患者によって処方の行方は左右されることを常識として自明のものと捉えている。
たとえば歯痛のため健常者が痛み止めの薬を求めた場合、医師から一週間ほどの薬が処方されたとしよう。ところが二日目にして痛みが消えたとするならば、残り五日間の痛み止めを服用する患者が存在するだろうか?目的は歯痛を消すことにあるのだから、歯痛が消えれば当然のことながら患者が痛み止めの薬を中止することが自然だ。だが歯痛の痛みがどうであれ、医師から一週間の歯痛止めの処方がなされた場合、支援員は利用者の歯痛にさほど注目することもなく、処方箋通りに一週間を服薬させることになる。
あるいは医師から「タバコはやめなさい。日本酒なら一合程度、ビールならコップ一杯」と指摘されて、「はい、わかりました」とその指摘を実践する健常者など絶対に存在しない。健常者に医師から放たれたその指摘が、対象が知的障害者となると、その診察に同席した支援員によっては、医師の指摘をそのまま実施する場合が決してめずらしくない。その際、無論「医師の指示命令の下に」という前提で利用者に対する禁煙が強制されたりすることはままあることだ。

知的障害の特性を理解しない医師が多数を占めている現在、医師が健常者への処方と同じ配分基準で薬の処方をすることにまちがいなく問題があると私は考えている。その根拠は、知的障害における服薬についての人権のありかたである。知的障害のある利用者の人権が尊重されているとは到底考えられないのだ。
そんなある日、私の疑問が無視されなくなった出来事が起こった。2011年4月1日、私は施設長に就任したのである。つまり施設内における権力の側に立った。これはそれまで私の問題提起を曖昧ながら無視に帰結されていた状態が消えることを意味していた。その自覚をもった私は入念に施設内で「根回し」をはじめた。それが治療とは何か?という点のワークショップであった。そういった意識の共有状態をつくりあげておいて、精神科の医師に対してひとつの質問を発しさせた。回答は私の予想以上に明確であった。
「服薬根拠はわかりません」――――――この言葉がはじまりであった。服薬根拠がわからないままに医師は利用者に対して薬(主に精神薬等)の処方をしていた事実が露わになった。そのことに職員たちは何を思い、何を考えるのだろう?

いずれにせよ当施設の減薬・断薬への取組みのスタートラインは医師によるこの回答であった。






COMMENT ON FACEBOOK